近現代
NHK わたしの自叙伝 6.[学問・研究2]有賀喜左衛門/宮本常一
有賀喜左衛門(あるが・きざえもん)1897(明治30)~1979(昭和54) 農村社会学者 長野県出身
「民族の心をもとめて」~京大から東大へ移り、柳宗悦に出会い朝鮮美術の美しさに目を開かされ、柳田國男とも出会い日本学を学ぶ。それぞれの民族には「民族の心」とでもいう固有な美的特質があることに気づく。
宮本常一(みやもと・つねいち)1907(明治40)~1981(昭和56) 民俗学者 山口県出身
「民俗学との出会い」~渋沢敬三の勧めで民俗文化の発掘者に。柳田國男とも親交。全国を旅して優れた語り部に出会い、多くの記録を残した。民衆の生活が滲み出た民俗学を確立。先を急いじゃいかん、すべてがロングランなんだ。
NHK わたしの自叙伝 7.[学問・研究3]井上光貞/江上波夫
井上光貞(いのうえ・みつさだ)1917(大正6)~1983(昭和58) 日本史(古代)学者 東京都出身
「戦時下に古代を読む」~天皇家起源は民族叙事詩とは無関係であるとする書物は、発禁書ながら印象深い読書だった。永井荷風「濹東綺譚」の中に真実を求める姿勢を感じたことが、歴史学への関心の起こりだった。
江上波夫(えがみ・なみお)1906(明治39)~2002(平成14) 東洋史(考古)学者 山口県出身
「黄塵万丈モンゴルをゆく」~北京に遊学、中国・モンゴル文化のモザイク文化圏=蒙古を旅した。農耕文化と遊牧文化の違いと融合の観察から「騎馬民族日本征服説」が誕生。生活文化が社会を規定することが判った。
NHK わたしの自叙伝 8.[学問・研究4]直良信夫/末永雅雄
直良信夫(なおら・のぶお)1902(明治35)~1985(昭和60) 考古学者(古生物) 大分県出身
「明石原人発見」~明石の海岸で人骨化石を発見、東大に鑑定を依頼するも、学歴偏重の学界の閉鎖性に泣く。空襲で化石を焼失して茫然自失。学界の後ろ盾の無い研究者の苦い思い出。
末永雅雄(すえなが・まさお)1897(明治30)~1991(平成3) 考古学者(古墳) 大阪府出身 橿原考古学研究所
「古墳遍歴」~少年時代、御陵の中で遊んだことが考古学研究に進んだきっかけ。古墳出土の鉄製品や石舞台の研究を手がけ、古墳を上空から観察する「航空古墳研究」の手法で新境地を開く。
NHK わたしの自叙伝 9.[学問・研究5]本田正次/木原均
本田正次(ほんだ・まさじ)1897(明治30)~1984(昭和59) 植物学者 熊本県出身
「草木を友に」~栃木山奥での新種発見の思い出。植物の老いと時間感覚とは何か。草花観察と種の消失を見届けてきたこと。戦時中、小石川植物園長として遭遇した様々な困難。植物はわが師・わが友・わが命。
木原均(きはら・ひとし)1893(明治26)~1986(昭和61)遺伝学・生物学者 東京都出身
「小麦をえらんだ道」~大学の先輩・坂村徹と出会い小麦研究の道へ。ドイツの研究者と意見を交わした在外研究時代。イランへの学術探検で小麦の祖先を発見した。いい研究をやってもその成功を本人が見ることは稀。
NHK わたしの自叙伝 10.[教育・宗教1]林竹二/大村はま
林竹二(はやし・たけじ)1906(明治39)~1985(昭和60) 教育学者・教育家 栃木県出身
「子供とともに育つ」~全国の小中学校で「人間について」200回を超える授業。退官後も各地で対話を続ける。成績というのは仮の姿、深い学習のある授業で成績の差は消える。子供は非常に大きな力を持っている。
大村はま(おおむら・はま)1906(明治39)~2005(平成17) 教育者 神奈川県出身
「教えつづけた50年」~戦後、新制中学での教育に無力さを感じた。子どもらの新聞切り抜きの「活字を見る目」に救われ、「やさしい言葉」でこそ本当に話し合えることに気づいた。出来ることを力一杯やらせれば子どもは伸びる。
NHK わたしの自叙伝 11.[教育・宗教2]城戸幡太郎/松前重義
城戸幡太郎(きど・まんたろう)1893(明治26)~1985(昭和60) 教育学者・教育家 愛媛県出身
「教育改革の旗の下に」~祖父の薫陶「自由であること」が教育観の基調。東北、北海道で生活綴り方運動と出会い、勤労主義から生活主義に転じた。弾圧も受けたが、戦後は「教育科学」を標榜した。
松前重義(まつまえ・しげよし)1901(明治34)~1991(平成3) 教育者 熊本県出身
「青年道場「望星学塾」の日々」~人生に悩んだとき聖書と内村鑑三に出会い教育を志す。無装荷搬送ケーブル実用化に尽力していた頃、デンマーク国民高等学校を訪問したことが後の望星学塾と東海大学設立につながった。若き日に汝の思想を培え。
NHK わたしの自叙伝 12.[文芸1]丹羽文雄/井上光晴
丹羽文雄(にわ・ふみお)1904(明治37)~2005(平成17) 作家 三重県出身
「母への愛憎」~寺の子として生まれるも勘当される。母をひとりの女として描き「非情な作家」といわれた。放縦な人生を送った母の晩年を看取り「煩悩即菩提」「悪人正機」を実感。母がいなければ小説家の自分が存在しなかった。
井上光晴(いのうえ・みつはる)1926(大正15)~1992(平成4) 作家 福岡県出身 「ガダルカナル戦詩集」
「海底炭坑の青春」~起きながら眠り、眠りながら起きる術を得た、長崎の海底炭坑での壮絶な環境下の労働。初恋と失恋。霊媒師と香具師の騙しのテクニックに憧れた少年時代。それらが作家の原点となった。
NHK わたしの自叙伝 13.[文芸2]尾崎一雄/黒岩重吾
尾崎一雄(おざき・かずお)1899(明治32)~1983(昭和58) 作家 神奈川県出身 「暢気眼鏡」「虫のいろいろ」
「病と貧乏と芳兵衛と」~自らの土俗的な作品傾向には、生涯の大部分を過ごしている小田原が影響している。着物を質流ししていた貧乏生活、療養生活を経て得た死生観を語る。人間は本来無一物。
黒岩重吾(くろいわ・じゅうご)1924(大正13)~2003(平成15) 作家 大阪府出身
「わが闘病時代」~百万人に一人という奇病にかかり4年間闘病。人生を、人間を恨み、悪い事をしていない自分がなぜこんな目に、と嘆いたが、絶望と向き合うことで生きがいを見つけた。苦しみが生きがいになれば怖いものは何もない。
NHK わたしの自叙伝 14.[文芸3]大原富枝/田宮虎彦
大原富枝(おおはら・とみえ)1912(大正元)~2000(平成12) 作家 高知県出身 「婉という女」
「ふり返る青春」~高知の学生時代に友人が自殺、その頃から短歌を詠み始める。東京の学生と恋に落ちるが破局、戦後、男性の母親と34年ぶりに再会して慟哭。ふり返るのを自らに禁じていた「躓きの青春」を語る。
田宮虎彦(たみや・とらひこ)1911(明治44)~1988(昭和63) 作家 東京都出身 「足摺岬」
「父子のきずな」~父の愛を感じずに育ったことが創作意欲の原動力だった。スタンダール「赤と黒」やスタインベック「エデンの東」の父という存在に感銘を受け、父親の核心に触れる機会を得た。父親を小説に書くことで救われた。
NHK わたしの自叙伝 15.[文化・芸術1]新藤兼人/今井正
新藤兼人(しんどう・かねと)1912(明治45)~2012(平成24) 映画監督 広島県出身 近代映画協会
「一家離散の記憶」~三代続く宮大工だった実家が離散。姉は家を助けるために多額の結納金を用意したアメリカ移民へ嫁いだ。53年ぶりに姉との再会をカリフォルニアで果たす。時の流れはしょうがないものだ。
今井正(いまい・ただし)1912(明治45)~1991(平成3) 映画監督 東京都出身
「レッドパージの頃」~戦後、会社企画のみの映画界から独立、「青い山脈」制作。戦争に絡む映画はGHQの検閲、レッドパージで屑屋の元締に。沖縄を知らずして「ひめゆりの塔」を制作し大ヒット。苦難の中、夢中で映画に取り組んだ。
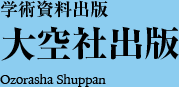
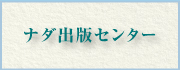
![NHK わたしの自叙伝 6.[学問・研究2]有賀喜左衛門/宮本常一](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_06_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 7.[学問・研究3]井上光貞/江上波夫](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_07_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 8.[学問・研究4]直良信夫/末永雅雄](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_08_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 9.[学問・研究5]本田正次/木原均](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_09_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 10.[教育・宗教1]林竹二/大村はま](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_10_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 11.[教育・宗教2]城戸幡太郎/松前重義](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_11_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 12.[文芸1]丹羽文雄/井上光晴](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_12_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 13.[文芸2]尾崎一雄/黒岩重吾](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_13_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 14.[文芸3]大原富枝/田宮虎彦](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_14_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 15.[文化・芸術1]新藤兼人/今井正](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_15_200.jpg)