近現代
NHK わたしの自叙伝 26.[学問・研究6]丹下健三/福山敏男
丹下健三(たんげ・けんぞう)1913(大正2)~2005(平成17) 建築家 大阪府出身 広島平和記念公園
「建築・道・ひろば・都市」~伝統を現代の建築技術の中にどう活かすか。建築が都市に並ぶ場合、文章でいえば文法が必要。木にたとえれば、幹とか枝をきちっと与えれば色々な形の花が咲いても全体の調和が保たれる。
福山敏男(ふくやま・としお)
1905(明治38)~1995(平成7) 建築史家 福岡県出身
「「古代建築史」修行五十年」~小泉八雲のことばに感銘受け、内務省造神宮使庁に。法隆寺の五重塔の落書きは、子どもたちの手習歌「難波津に咲くやこの花云々」とひらめいた。いつも新鮮な感覚を保つ。
NHK わたしの自叙伝 27.[学問・研究7]島秀雄/茅誠司
島秀雄(しま・ひでお)1901(明治34)~1998(平成10) 鉄道技術者 大阪府出身 東海道新幹線
「D51誕生の頃」~鉄道省に就職し大宮工場へ。C53の設計に参画、そしてD51で機関車の形と思想を確立したと思っている。「消えゆく」蒸気機関車はいいが、「滅びゆく」という形容詞は使いたくない。
茅誠司(かや・せいじ)1898(明治31)~1988(昭和63) 物理学者 神奈川県出身 東京大学総長
「南極観測のころ」~日本学術会議について思い出深く残っていることは、原子力問題、中国招待、そして南極観測。昭和32年1月25日オングル島に上陸、船は宗谷。乗り越えられない困難はなかった。
NHK わたしの自叙伝 28.[学問・研究8]早石修/河村郁
早石修(はやいし・おさむ)
1920(大正9)~2015(平成27) 医学者・細胞生物学 米国カリフォルニア州出身
「占領下の米国留学」~戦後の焼け跡の土から採取したバクテリアがのちの生化学研究に大きく寄与する酸素添加酵素の発見につながる。基礎研究と、開発途上国の研究者の受け入れを。研究はやってみないとわからない。
河村郁(かわむら・いく)1902(明治35)~1990(平成2) 看護学 長野県出身 看護協会
「結核根絶をめざして」~近江八幡のヴォーリズさんから看護婦教育とサナトリウムの管理を依頼された。結核予防を社会的な運動へ。日本結核予防協会診療センター、結核療養所晴嵐荘ができた。また訪問看護を始めた。
NHK わたしの自叙伝 29.[学問・研究9]平澤興/湯浅八郎
平澤興(ひらさわ・こう)
1900(明治33)~1989(平成元) 医学者・脳神経解剖学 新潟県出身 京都大学総長2期
「京の田舎人」~村医者になるという親との約束を破り学者の道に進むも兵糧を絶たれた。スイス留学でモナコフ先生から「わかるとわかったつもりとは違う」と言われ、全情熱を研究にかけた。
湯浅八郎(ゆあさ・はちろう)
1890(明治23)~1981(昭和56) 教育者・昆虫学 東京都出身 同志社大総長 国際基督教大総長
「両大戦下でのアメリカ体験」~真珠湾攻撃の朝、メイン州の教会でキリスト者の平和責任と題して説教を。原爆投下をニューヨークで聞いた。平素は殺伐粗暴な地下鉄車内では誰も顔を上げなかった。
NHK わたしの自叙伝 30.[教育・宗教3]葉上照澄/小笠原英法
葉上照澄(はがみ・しょうちょう)1903(明治36)~1989(平成元) 天台宗僧侶・大阿闍梨 岡山県出身
「敗戦と千日回峰行」~長い歴史の比叡山延暦寺でも50人と達成者のいない千日回峰満行者。敗戦によって仏門を志したが、戦勝国のマッカーサーを一目見てやろうと横浜まで出向いたことも。一切は巡り合わせ。
小笠原英法(おがさわら・えいほう)1914(大正3)~2002(平成14) 女優・尼僧 広島県出身
「舞台を捨てて仏門へ」~宝塚歌劇団星組トップの座から女優へ転身、結婚と離婚…成功と失敗、山あり谷ありの人生を送ったのち仏門にという稀有な人生を振り返る。「生きているんですから精一杯生きて」
NHK わたしの自叙伝 31.[文芸4]中村真一郎/山本茂實
中村真一郎(なかむら・しんいちろう)1918(大正7)~1997(平成9) 作家・小説家 東京都出身 「四季」四部作
「母と女のあいだに」~幼いころ死別した母になるという異様な夢を見た。その経験から自分と母、女性についてさまざまに思索を重ね、集大成四部作を構想した。文学者は現実と夢の世界を行ったり来たりする。
山本茂實(やまもと・しげみ)1917(大正6)~1998(平成10) 作家 長野県出身 「あゝ野麦峠」
「野麦峠への道」~人の心の美しさ、汚さを、しみじみと私の体に教え込んでくれたのは、松本の町を毎日車をひいて野菜物を売っていた10年間と12年間のもみくちゃにされた「葦」の生活。何が幸せになるかわからない。
NHK わたしの自叙伝 32.[文芸5]石垣りん/松田解子
石垣りん(いしがき・りん)1920(大正9)~2004(平成16) 詩人 東京都出身
「わたしの前に詩集が三つ」~稼いだお金で自分のしたいことをしようと、14歳で銀行に就職したが、生きるのに精一杯で他者の幸せに加担することもなく詩を書いていた。詩は自分でもはっきり掴むことができないものを形にして見せる。
松田解子(まつだ・ときこ)1905(明治38)~2004(平成16) 作家 秋田県出身 「おりん口伝」
「はるかなる銅山」~鉱山は私に命を与えてくれた。「父と兄が道楽者で身代を食いつぶし、オカアは銅山にきて再婚して8人の子持ち。自分の腹から出した一人や二人、自分の腕で養わなきゃだめだ」母の告白が耳に。
NHK わたしの自叙伝 33.[文化・芸術4]高光一也/八木一夫
高光一也(たかみつ・かずや)1907(明治40)~1986(昭和61) 画家 鳥取県出身 浄土真宗
「仏の道と絵の道と」~父は道を求めて放浪もした。工業高校図案絵画科へ入ったが、ゴッホの絵のようなものを描きたいと思い退学を考えた。自分というものがすっかり判らなくなった時に、青天の霹靂のように仏の道に入った。
八木一夫(やぎ・かずお)1918(大正7)~1979(昭和54) 陶芸家 京都府出身 走泥社
「オブジェ焼誕生のころ」~幼いころから図画工作の成績も芳しくなく、美の才能に乏しいと周囲から思われていたが、それをはねのけて新しい焼物を生み出すまでを振り返る。飢えている状態でないとものを発見できない性分だ。
NHK わたしの自叙伝 34.[文化・芸術5]寿岳文章/大江巳之助
寿岳文章(じゅがく・ぶんしょう)1900(明治33)~1992(平成4) 英文学者・書誌学 兵庫県出身
「紙すき村 行脚のころ」~ウィリアム・ブレイクの書誌研究から和紙研究へ。昭和12~15年、日本全国の紙漉き地を巡り歴史地理学的に調査。フィールドワークとして初の試みだった。「日本の紙」(1967)を英文で出版した。
大江巳之助(おおえ・みのすけ)1907(明治40)~1997(平成9) 文楽人形師 徳島県出身
「人形に魂をこめて」~人形師の家に生まれながら人形師を志さなかったが、グラフ誌で見た大阪文楽座の写真に深く感銘を受け修行し始めた。人形作りの真髄を学んでいった過程を振り返る。人形は舞台にかけて作れ。
NHK わたしの自叙伝 35.[文化・芸術6]手塚治虫/田河水泡
手塚治虫(てづか・おさむ)1928(昭和3)~1989(平成元) 漫画家 大阪府出身 「鉄腕アトム」
「こども漫画33年」~医者なのになぜ漫画家に? 描きだしたのは小学校2,3年頃。コンプレックスの裏側でがむしゃらに取り組んでいた。僕の漫画は、「生きる」ということに執着をもったものが多い。漫画はハングリーアート。
田河水泡(たがわ・すいほう)1899(明治32)~1989(平成元) 漫画家 東京都出身 「のらくろ」
「のらくろ誕生前後」~大正の終わり頃、芸術運動に参加して抽象画の世界で暴れた。漫画を借りて読む子どもたちを励ましてやりたかった。主人公が読者よりもっと底辺にいると思えば、読者は優越感で笑うことができる。
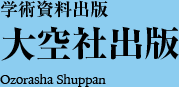
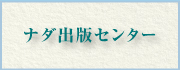
![NHK わたしの自叙伝 26.[学問・研究6]丹下健三/福山敏男](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_26_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 27.[学問・研究7]島秀雄/茅誠司](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_27_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 28.[学問・研究8]早石修/河村郁](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_28_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 29.[学問・研究9]平澤興/湯浅八郎](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_29_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 30.[教育・宗教3]葉上照澄/小笠原英法](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_30_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 31.[文芸4]中村真一郎/山本茂實](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_31_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 32.[文芸5]石垣りん/松田解子](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_32_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 33.[文化・芸術4]高光一也/八木一夫](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_33_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 34.[文化・芸術5]寿岳文章/大江巳之助](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_34_200.jpg)
![NHK わたしの自叙伝 35.[文化・芸術6]手塚治虫/田河水泡](https://www.ozorasha.co.jp/upload/images/jijoden_35_200.jpg)